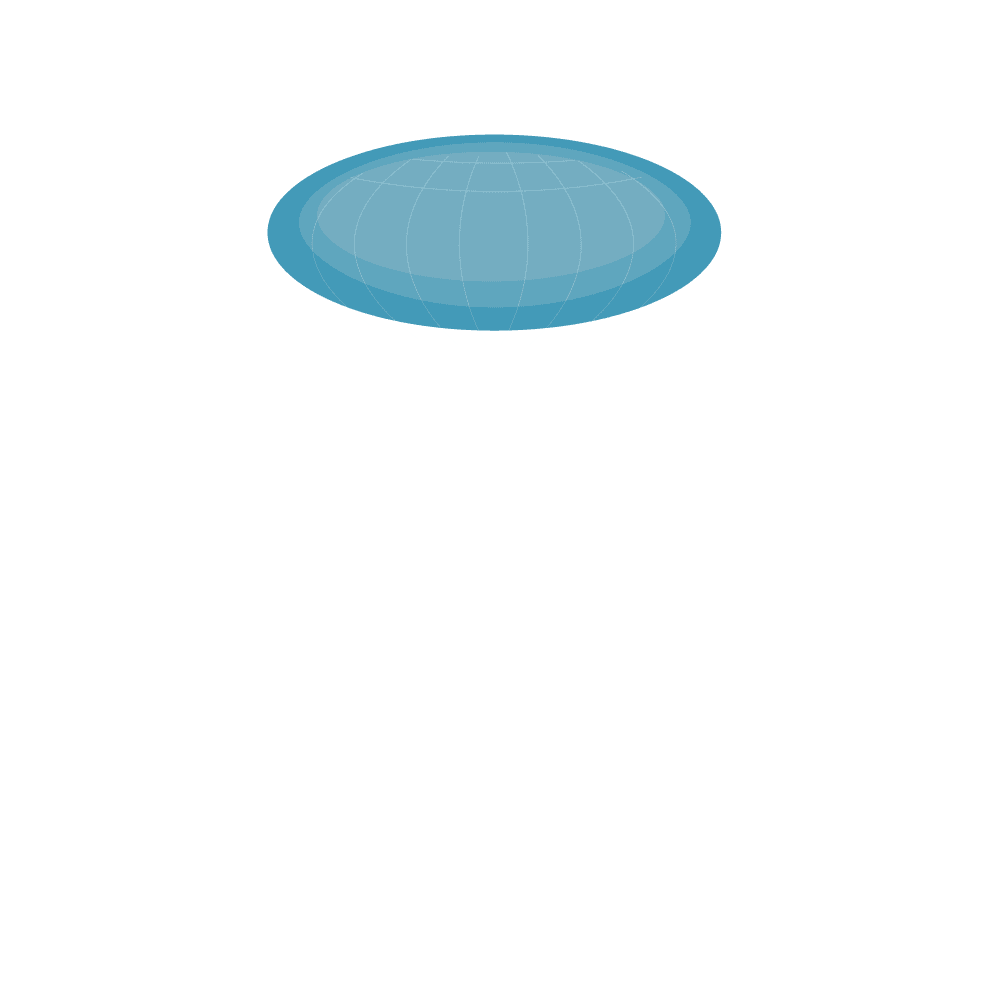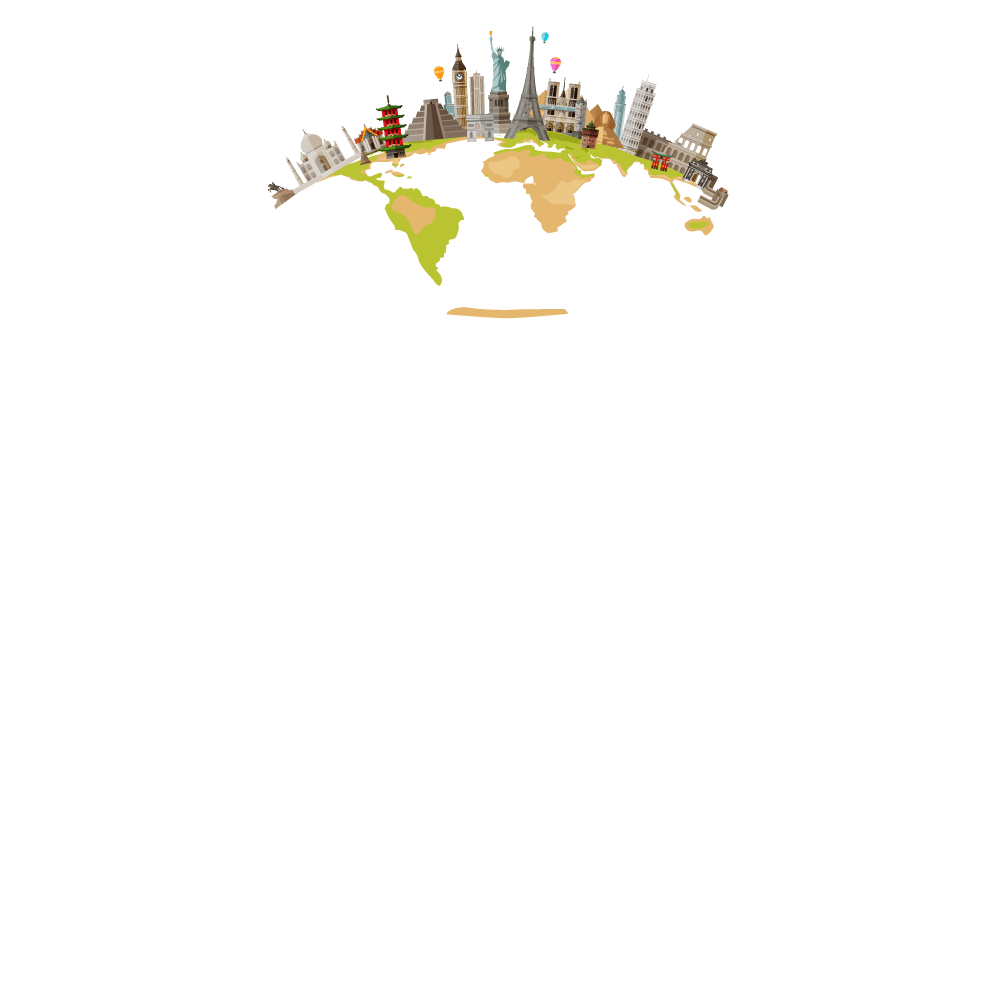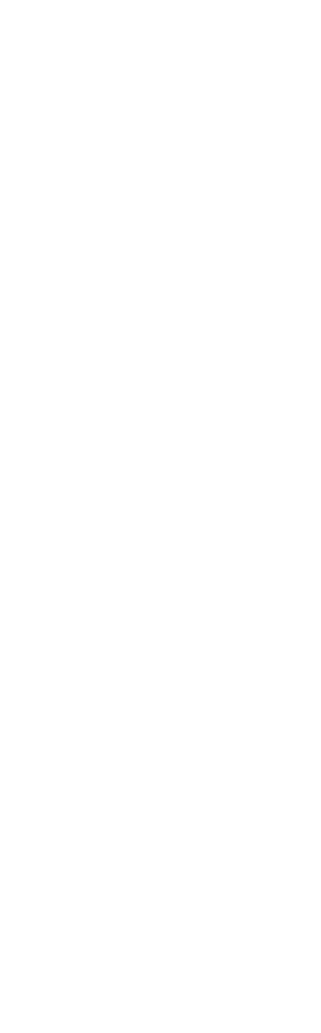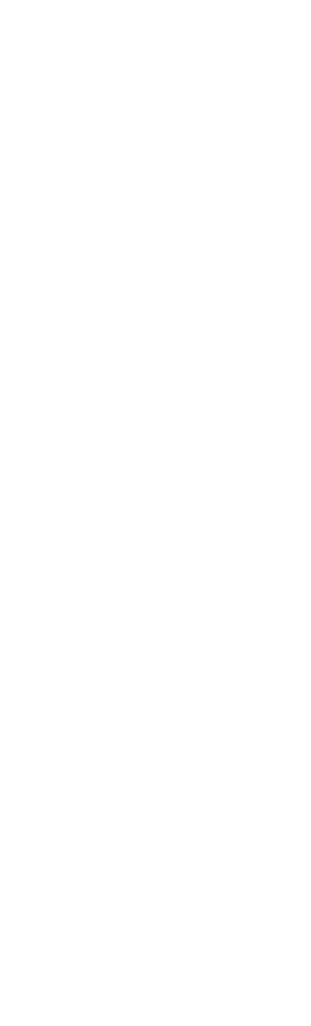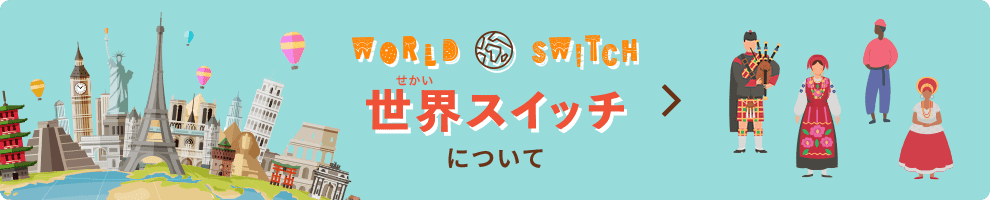震災を経験し「海と生きる」まち、気仙沼
いいね
910
2025/01/23

日本
こんなことがかいてあるよ!
- 宮城(みやぎ)県の気仙沼(けせんぬま)には、2011年3月11日、とても大きな地震と津波が来たんだ。
- でも、震災の後の気仙沼は、漁師さんや漁業を大事にしたり、みんなで相談して安全に暮らせるまちをつくったりして、今はとても活気のあるまちになっているんだ!
みんなは、宮城県の気仙沼というまちを知っているかな?
気仙沼は、日本の北の方にあって、山や海に囲まれた自然が豊かなまちなんだ。
山ではいろんなお野菜が取れる。そして何より、気仙沼にはとても大きな漁港があるから、すっごくおいしい魚が、たくさん食べられるんだ!

Photo by Tomoko Ito
2011年3月11日、そんな気仙沼に、とても大きな地震と津波が来たんだ。
その時には、たくさんの家がこわれ、たくさんの人が亡くなった。きっと、とても悲しい気持ちになった人たちもたくさんいたね。
でも、気仙沼の人たちは、大きな地震と津波にも負けず、何年もかけて、まちをもう一度つくり直してきたんだ!
そんな気仙沼は、今、どんなまちになっているんだろう?
気仙沼で地域を良くする活動をする、菅原昭彦(すがわらあきひこ)さんという人にお話を聞いたよ。

Photo by Tomoko Ito
「日本一漁師さんを大切にするまち」になる
気仙沼には、日本の中でもとっても大きな漁港があって、世界中からおいしい魚を取ってきた漁師さんたちがたくさん集まるんだ!
例えば、カツオとメカジキとサメは日本一たくさん取れるし、ほかにも、ウニやアワビ、マグロなど、いろんな種類のお魚が取れるそうだよ。

Photo by Motomi Souma
それに、リアス海岸と呼ばれるジグザグの海岸のおかげで、カキやワカメも育てることができるんだ。
海のすぐそばにある山から川をつたって栄養が流れてくるから、エサをあげなくても、海の中で自然と育つんだって。

Photo by Motomi Souma
気仙沼には、こんなふうに、昔から漁業がまちを支えてきた歴史があるんだ。
でも、2011年に来た大きな津波で、そんな大事な漁港もこわれてしまった。
漁港がこわれてしまったら、船が入って来られない。船が入って来られないと、市場にお魚を並べることができなくなるから、まちのお金が少なくなって、みんな困ってしまったんだ。
こんな大変なことがあったから、気仙沼の人たちは、まちにとって漁業がとても大切なんだということを、改めて感じたんだって。
そこで震災の後に決めたのが、「日本一漁師さんを大切するまち」になること!
まちでいろいろな活動ができるのも、漁師さんが時には危険な海で、がんばってお魚を取ってきてくれているからなんだよね。
そんな感謝の気持ちをこめて作られたのが、漁師さんのためのおふろ「鶴亀(つるかめ)の湯」と、朝食が食べられるお店「鶴亀食堂」なんだ。

Photo by Motomi Souma
漁師さんは、遠くにお魚を取りに行っている間、船の中でシャワーを浴びるんだよ。だから帰ってきたらゆっくりおふろに入りたいし、おいしいご飯も食べたいよね。
港にこのおふろや食堂があることで、漁を終えた漁師さんたちが帰ってくることが楽しみになるといいな、という想いをこめてつくられたんだって。

Photo by Motomi Souma
朝食の食堂では、もちろんおいしい魚のメニューがたくさん食べられるよ。漁師さんに「ごくろうさまです」と伝えるメッセージや、長い間海にいることも多い漁師さんに町の様子を伝えるための新聞もはられていたよ。

Photo by Motomi Souma
そして、漁師さんに感謝するためには、漁師さんがどんなふうに漁をしているのか、知ることも大事だよね。そこで、震災の後に新しく作られた漁港の建物の中には、漁師さんの仕事の様子や気仙沼の漁業について知ることができる展示も作ったんだ。
例えば、下の写真は漁師さんが乗っている船の中をまねして作った模型なんだ。前に立ってみたら、みんなも漁師さんの気分になれそうだね!

Photo by Motomi Souma
気仙沼の漁業や食文化では、みんなが学校で習う「SDGs」にもつながる行動が、昔からふつうのこととして行われているんだ。
例えば、最近では、お魚を取りすぎて、海からお魚が減ってしまうことが問題になっている。でも、気仙沼では、みんなが長いあいだお魚を取って暮らしていけるように、必要以上にお魚を取る人はいないんだ。
それから、海から取ったお魚は、おいしい身だけじゃなくて、骨はおせんべいにして食べたり、皮はおさいふにして使ったりと、むだにしないんだって。さらに、お魚を全部おいしく食べるための伝統的な料理も、たくさんあるんだ。
こんなふうに、気仙沼の漁業や食文化には、これからみんなが大事にしたい考え方がたくさんつまっているんだ。
だから気仙沼では、自然に感謝して、食べ物に感謝する心をこれからも大事にしていくんだって。そして、その気持ちを、ほかの地域の人にも伝えていこうとしているんだ。

お店の目の前の海で育てたカキが食べられる、「ヤマヨ食堂」。
Photo by Motomi Souma
みんなで作った、海が見える防潮堤(ぼうちょうてい)
昔から気仙沼でまちをよくするための活動を続けてきた菅原さんは、震災の後もいろんなことをしたんだ。
そのひとつが、また大きな津波が来た時にまちを守るための、防潮堤(ぼうちょうてい)と呼ばれる大きなかべを作ること。これを作ることは、まちの人たちの安全な暮らしを守るためにと、宮城県で決められたことなんだ。
津波のひがいを受けたほかのまちでは、海の手前に高いコンクリートのかべを作ったところもある。
でもそうすると、まちから海が見えなくなってしまうよね。
漁業がまちを支えてきた気仙沼は、昔から、海といっしょに生きてきた。だから、海が見えなくなると悲しい気持ちになるだけじゃなく、海とのつながりがなくなってしまうように感じて、とてもこわい気持ちになってしまうんだって。
そこで、菅原さんは気仙沼の人みんなが参加できる会議を開いて、どんな防潮堤にするかをみんなで話し合うことにしたんだ。
その会議には一度に100人以上が集まることもあって、開いた回数も、なんと1年間で100回以上!
さらに、みんなの意見をまとめて、いろんなデザインの防潮堤を実際に作って見比べながら、どんなものが一番まちにとって良いかを、3年間くらいかけて考えていったんだ。
そうして完成したのが、いつもは海の中にかくれていて、津波が来た時だけコンクリートのかべが立ち上がる、「フラップゲート式」と言われる防潮堤なんだ。

いつもは見えていないけど、この地面の下に大きなかべがかくれているんだって。
Image via 気仙沼市
この防潮堤があるから、どんな津波が来ても絶対に安心ということはないかもしれない。でも、「海といっしょに暮らしたい」というまちの人の願いがかなう防潮堤にできたのは良いことだったと、菅原さんは教えてくれたよ。
それに、気仙沼が震災の後に決めたまちづくりの合言葉は、「海と生きる」なんだ。菅原さんは、「これは、海と生きてきた自分たちにぴったりの言葉だよ」と話していたよ。

Photo by Motomi Souma
ボランティアで来た人たちが、新しい住民に
地震や津波が起こったことは悲しいし、決して忘れることはできない気仙沼のまちの歴史のひとつだ。
でも、震災の後、まちに良い変化も起こったそうなんだ。
そのひとつが、新しくまちに住む若い人たちが増えたこと!
震災が起こったすぐ後には、日本中からたくさんのボランティアの人たちが気仙沼にかけつけたんだ。その中には、気仙沼に初めて来る大学生や、気仙沼で生まれ育ったけど別のまちで暮らしていた若い人たちもたくさんいた。
その人たちは、気仙沼の人たちが、「自分たちでまちを立て直していくんだ」という強い気持ちで行動していたことに、感動したんだって。
それで、震災のボランティアが終わってからも気仙沼に住み続けたり、地元である気仙沼にもどってきたりする人がたくさん出てきたんだ。
震災から14年が経った2025年の今、そうして住み始めた若い人たちが、気仙沼でいろんな新しい取り組みをして、まちをもり上げているんだって。

気仙沼の外からきた大学生や地元の若い人たちがいっしょにまちを歩いて、自分たちでマップを作っているんだ! 地元の人たちに話を聞いて、それを絵にまとめているよ。
Image via 気仙沼市
それに、気仙沼の人たちは、震災の後にボランティアに来た人たちに、自分たちのまちを案内してあげていたんだって。
それを見た菅原さんは、「みんなの暮らしに近い、新しい観光を考えよう!」と思って、気仙沼の一番のみりょくである食べ物をもっと楽しんでもらえるツアーやキャンペーンをつくることにした。
そのおかげで、いろんな場所から気仙沼に人が遊びに来るようになって、気仙沼の良さを知る人も増えたんだ!

大人たちと小学生がいっしょに活動する、「畑づくり大作戦」! さつまいもの畑をみんなで耕しているよ。
Image via 気仙沼市
気仙沼の人たちは、震災があって自然のこわさも改めて知ったけど、それでも海や自然といっしょに生きることを選んでいる。
そして気仙沼には、まちが大好きで、「まちのために、自分にできることは何かな?」って考えている人たちがたくさんいる。その気持ちは、震災というつらい経験を乗りこえて、もっと大きくなっているみたいなんだ。
みんなも気になったら、家族や友達と気仙沼に行ってみてね。きっとまちの人たちから、たくさんのエネルギーをもらえるよ!
情報提供:IDEAS FOR GOOD(ハーチ株式会社)