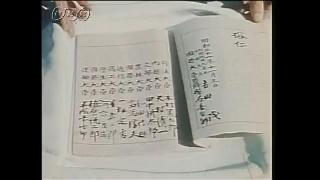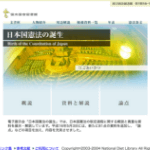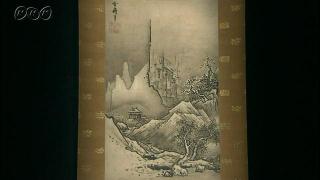戦後の日本の発展と日本国憲法
まとめ
歴史
第二次世界大戦後、日本は日本国憲法を制定し、平和な国家として発展してきました。国民生活が向上し、国際社会の一員として日本が歩んできた道のりを学ぼう。
戦後の日本のはじまり
第二次世界大戦が終わり(1945年)、日本はアメリカなどの連合国に降伏しました。
終戦後、日本はGHQ(連合国軍総司令部)による占領下で、政治や社会の仕組みを大きく変えざるを得なくなります。
このとき進んだ民主化政策や経済の立て直しが、戦後日本の発展につながっていくのです。
終戦後、日本はGHQ(連合国軍総司令部)による占領下で、政治や社会の仕組みを大きく変えざるを得なくなります。
このとき進んだ民主化政策や経済の立て直しが、戦後日本の発展につながっていくのです。
日本国憲法の制定
制定された年:1946年公布、1947年施行
戦後の新しい国づくりのために、憲法が全面的に改正されました。
民主主義の考え方を取り入れた日本国憲法が誕生し、現在に至るまでの日本の基本ルールになっています。
三大原則
国民主権:政治の中心は国民である
平和主義:戦争を放棄し、平和をめざす(憲法第9条)
基本的人権の尊重:自由や平等など、人が生まれながらにもつ権利を大切にする
天皇の地位
天皇は「日本国の象徴」と位置づけられ、政治的な実権はもたない立場になりました。
戦後の新しい国づくりのために、憲法が全面的に改正されました。
民主主義の考え方を取り入れた日本国憲法が誕生し、現在に至るまでの日本の基本ルールになっています。
三大原則
国民主権:政治の中心は国民である
平和主義:戦争を放棄し、平和をめざす(憲法第9条)
基本的人権の尊重:自由や平等など、人が生まれながらにもつ権利を大切にする
天皇の地位
天皇は「日本国の象徴」と位置づけられ、政治的な実権はもたない立場になりました。
経済復興と高度経済成長
復興期
戦争で焼け野原になった都市や工場を建て直し、GHQの援助を受けながら日本は再スタート。
1951年にはサンフランシスコ平和条約に調印し、1952年に占領が終わります。
高度経済成長
朝鮮戦争による特需や、アメリカとの貿易などで日本企業が急速に発展。
自動車・家電・鉄鋼などの工業が伸び、いわゆる「3C(カー、クーラー、テレビ)」などが庶民の生活に普及。
東京オリンピック(1964年)や新幹線の開通がシンボル的な出来事でした。
公害や社会問題
産業の発展が進む一方で、工場排水や排気ガスによる大気や水質の汚染が深刻化。四大公害病が発生し、環境保護の取り組みが叫ばれました。
戦争で焼け野原になった都市や工場を建て直し、GHQの援助を受けながら日本は再スタート。
1951年にはサンフランシスコ平和条約に調印し、1952年に占領が終わります。
高度経済成長
朝鮮戦争による特需や、アメリカとの貿易などで日本企業が急速に発展。
自動車・家電・鉄鋼などの工業が伸び、いわゆる「3C(カー、クーラー、テレビ)」などが庶民の生活に普及。
東京オリンピック(1964年)や新幹線の開通がシンボル的な出来事でした。
公害や社会問題
産業の発展が進む一方で、工場排水や排気ガスによる大気や水質の汚染が深刻化。四大公害病が発生し、環境保護の取り組みが叫ばれました。
戦後の民主化と社会の変化
教育改革
学校制度が改められ、6・3・3・4制(小・中・高・大学)を基本とする制度になりました。男女共学も推進されます。
労働組合の結成
労働者の権利や賃金を守るために、労働組合が活発化し、ストライキなどの行動をとることもできるようになりました。
婦人参政権の確立
女性が政治に参加することも認められ、選挙権や被選挙権が与えられました。男女平等の考え方が広がっていきます。
学校制度が改められ、6・3・3・4制(小・中・高・大学)を基本とする制度になりました。男女共学も推進されます。
労働組合の結成
労働者の権利や賃金を守るために、労働組合が活発化し、ストライキなどの行動をとることもできるようになりました。
婦人参政権の確立
女性が政治に参加することも認められ、選挙権や被選挙権が与えられました。男女平等の考え方が広がっていきます。