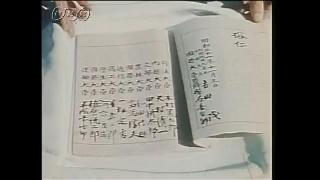武士がおさめた鎌倉・室町時代
まとめ
歴史
それまで貴族につかえていた武士は、しだいに力を持ち、政治に関わるようになってきます。源平の戦いから、源頼朝が開いた鎌倉幕府(かまくらばくふ)やその後の時代の室町幕府(むろまちばくふ)について学ぼう。
武士の力が強まり、武士がおさめる時代へ
平安時代には、天皇や貴族が政治の中心にいましたが、時がたつにつれて武士が力をつけていきます。
平安時代の後半になると、地方では武士団が土地を守り、やがて都の政治にもかかわりを持つようになりました。
そんな武士たちが政治をおさめるようになったのが、鎌倉時代と室町時代です。
平安時代の後半になると、地方では武士団が土地を守り、やがて都の政治にもかかわりを持つようになりました。
そんな武士たちが政治をおさめるようになったのが、鎌倉時代と室町時代です。
鎌倉幕府の始まり
源頼朝の活躍
平氏を倒し、頼朝は朝廷から征夷大将軍に任命されます。これをきっかけに、鎌倉に武家の政府、鎌倉幕府が開かれました。
御恩と奉公
頼朝は家来の武士たち(御家人)に土地などのごほうび(御恩)を与え、御家人は戦いがあれば主君に協力する(奉公)という仕組みをつくりました。
北条氏の執権政治
頼朝の死後、北条氏が幕府の実権をにぎり、執権として政治を動かしました。
承久の乱や元寇(モンゴル襲来)のときにも武士の団結力で乗り切ったのが、この鎌倉幕府の特徴です。
平氏を倒し、頼朝は朝廷から征夷大将軍に任命されます。これをきっかけに、鎌倉に武家の政府、鎌倉幕府が開かれました。
御恩と奉公
頼朝は家来の武士たち(御家人)に土地などのごほうび(御恩)を与え、御家人は戦いがあれば主君に協力する(奉公)という仕組みをつくりました。
北条氏の執権政治
頼朝の死後、北条氏が幕府の実権をにぎり、執権として政治を動かしました。
承久の乱や元寇(モンゴル襲来)のときにも武士の団結力で乗り切ったのが、この鎌倉幕府の特徴です。
室町幕府の成立
建武の新政と足利尊氏
鎌倉幕府が倒れたあと、後醍醐天皇は建武の新政で天皇中心の政治を目指しましたが、武士たちの不満が高まり、足利尊氏が新政から離れて自分の政府をつくりはじめます。
室町幕府のはじまり
京都の室町という場所に幕府をおいたことから「室町幕府」と呼ばれます。足利尊氏が征夷大将軍となり、武士が政治をおさめる仕組みがつづきました。
足利義満のころ
室町幕府がもっとも安定したのが3代将軍の足利義満のときとされます。金閣を建て、文化や外交が発達した時代でもありました。
鎌倉幕府が倒れたあと、後醍醐天皇は建武の新政で天皇中心の政治を目指しましたが、武士たちの不満が高まり、足利尊氏が新政から離れて自分の政府をつくりはじめます。
室町幕府のはじまり
京都の室町という場所に幕府をおいたことから「室町幕府」と呼ばれます。足利尊氏が征夷大将軍となり、武士が政治をおさめる仕組みがつづきました。
足利義満のころ
室町幕府がもっとも安定したのが3代将軍の足利義満のときとされます。金閣を建て、文化や外交が発達した時代でもありました。
鎌倉・室町時代のくらしや文化
武家の政治
武士が土地や人を治めるいっぽう、朝廷は京都で名目的な役割をつづけました。
建武の新政の失敗と南北朝
天皇が2つに分裂し、京都をめぐって争った時期がありましたが、最終的に北朝と室町幕府が力をもって統一していきます。
文化の発展
武士の暮らしが広がるなかで、禅の心を重視した文化も人気に。室町時代には能や狂言、生け花・茶の湯などが発達しました。
金閣や銀閣などの建築も有名ですね。
武士が土地や人を治めるいっぽう、朝廷は京都で名目的な役割をつづけました。
建武の新政の失敗と南北朝
天皇が2つに分裂し、京都をめぐって争った時期がありましたが、最終的に北朝と室町幕府が力をもって統一していきます。
文化の発展
武士の暮らしが広がるなかで、禅の心を重視した文化も人気に。室町時代には能や狂言、生け花・茶の湯などが発達しました。
金閣や銀閣などの建築も有名ですね。
まとめ
鎌倉・室町時代は、天皇や貴族中心の時代から大きく変わって、武士がおさめる時代になりました。
・鎌倉時代では源頼朝が幕府を開き、御恩と奉公の仕組みで武士たちをまとめあげました。
・室町時代では足利尊氏が幕府をつくり、京都を中心に将軍が政治を動かしながら、禅の文化や美しい建築が花開きました。
このように武士の世の中が根付くことで、日本の政治のあり方も大きく変わり、それが戦国時代へとつながっていきます。
・鎌倉時代では源頼朝が幕府を開き、御恩と奉公の仕組みで武士たちをまとめあげました。
・室町時代では足利尊氏が幕府をつくり、京都を中心に将軍が政治を動かしながら、禅の文化や美しい建築が花開きました。
このように武士の世の中が根付くことで、日本の政治のあり方も大きく変わり、それが戦国時代へとつながっていきます。
動画で学ぼう!(NHK for School)
-
 NHK
01:10
源頼朝は、有力な家来を守護や地頭に任命し、幕府の力を強めたことがわかる。
NHK
01:10
源頼朝は、有力な家来を守護や地頭に任命し、幕府の力を強めたことがわかる。 -
 NHK
02:31
鎌倉幕府(かまくらばくふ)のもとでは、「いざ鎌倉」と幕府のために働くことが奉公であり、領地を守ってくれたり、与えたりすることがご恩であることがわかる。
NHK
02:31
鎌倉幕府(かまくらばくふ)のもとでは、「いざ鎌倉」と幕府のために働くことが奉公であり、領地を守ってくれたり、与えたりすることがご恩であることがわかる。 -
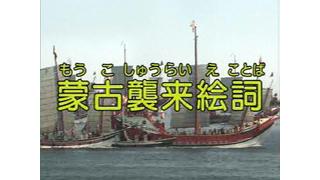 NHK
02:16
元寇のようすをえがいた蒙古襲来絵詞から、元軍のようすや戦い方がわかる。また、竹崎季長が、「ご恩と奉公」のために蒙古襲来絵詞を書いたことがわかる。
NHK
02:16
元寇のようすをえがいた蒙古襲来絵詞から、元軍のようすや戦い方がわかる。また、竹崎季長が、「ご恩と奉公」のために蒙古襲来絵詞を書いたことがわかる。 -
 NHK
01:47
鎌倉幕府のあと、室町幕府がどのようにして置かれたのかがわかる。
NHK
01:47
鎌倉幕府のあと、室町幕府がどのようにして置かれたのかがわかる。 -
 NHK
01:36
幕府の内乱によって、都が荒廃し、戦国の世へとつながっていく様子を知る。
NHK
01:36
幕府の内乱によって、都が荒廃し、戦国の世へとつながっていく様子を知る。