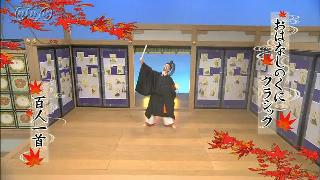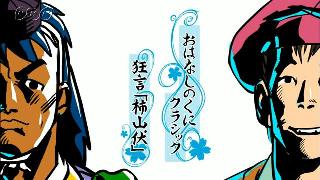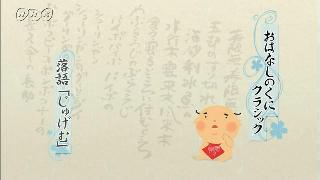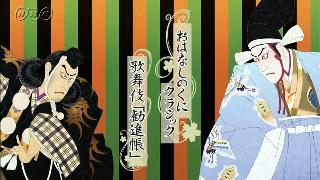古典(古文)
まとめ
物語
古典(古文)とは、古い時代に作られ、現在でも読みつがれている文学作品のことだよ。動画を見てみよう!
古文ってなに?
昔の日本で書かれた文章や文学作品を、今でも読みかえすときに「古文」とよぶよ。
今の日本語とはちがう言いまわしや言葉づかいをしているから、はじめはむずかしく感じるかもしれないね。
でも、その中には昔の人たちのくらしや考え方、物語のおもしろい世界がたくさんつまっているんだ。
今の日本語とはちがう言いまわしや言葉づかいをしているから、はじめはむずかしく感じるかもしれないね。
でも、その中には昔の人たちのくらしや考え方、物語のおもしろい世界がたくさんつまっているんだ。
古文の主な特徴
言葉づかいが今とちがう
古文には、今の日本語にはない言い方や文字の使い方がたくさんあるよ。
例えば「見る」を「みる」と書くのではなく、「みる」のあとに「める」を続けて書く形があったり、ひらがなの使い方も現代とはちがっていて、独特のリズムを感じることができるんだ。
歴史や文化がわかる
古文には、平安時代や鎌倉時代など、昔の人がどんなふうに暮らしていたかを知るヒントがあるんだ。
物語の世界が広がる
「源氏物語(げんじものがたり)」「枕草子(まくらのそうし)」など、有名な作品には今読んでもドキドキするストーリーがたくさんあるんだ。
古文には、今の日本語にはない言い方や文字の使い方がたくさんあるよ。
例えば「見る」を「みる」と書くのではなく、「みる」のあとに「める」を続けて書く形があったり、ひらがなの使い方も現代とはちがっていて、独特のリズムを感じることができるんだ。
歴史や文化がわかる
古文には、平安時代や鎌倉時代など、昔の人がどんなふうに暮らしていたかを知るヒントがあるんだ。
物語の世界が広がる
「源氏物語(げんじものがたり)」「枕草子(まくらのそうし)」など、有名な作品には今読んでもドキドキするストーリーがたくさんあるんだ。
古文を学ぶとどんないいことがある?
日本語のルーツを知ることができる
昔からの言葉づかいや文の組み立てを知ると、今私たちが使っている日本語がどのように変わってきたかがわかるよ。
歴史や文化をより深く理解できる
古文を読むことで、昔の人々の生活や行事、考え方がわかってくるよ。
物語を楽しむ力がつく
むずかしい言葉が出てきても、意味をしらべながら読むうちに読解力が高まるんだ。自分の知らなかった世界が広がって、ワクワクするよ。
古文は昔の日本の言葉で書かれた文や物語。むずかしく感じるかもしれないけれど、一つひとつ意味をしらべて読み進めていくと、昔の時代の空気や人々の思いが、今でもしっかりと伝わってくるんだ。ぜひ、いろいろな古文にふれてみてね。
昔からの言葉づかいや文の組み立てを知ると、今私たちが使っている日本語がどのように変わってきたかがわかるよ。
歴史や文化をより深く理解できる
古文を読むことで、昔の人々の生活や行事、考え方がわかってくるよ。
物語を楽しむ力がつく
むずかしい言葉が出てきても、意味をしらべながら読むうちに読解力が高まるんだ。自分の知らなかった世界が広がって、ワクワクするよ。
古文は昔の日本の言葉で書かれた文や物語。むずかしく感じるかもしれないけれど、一つひとつ意味をしらべて読み進めていくと、昔の時代の空気や人々の思いが、今でもしっかりと伝わってくるんだ。ぜひ、いろいろな古文にふれてみてね。